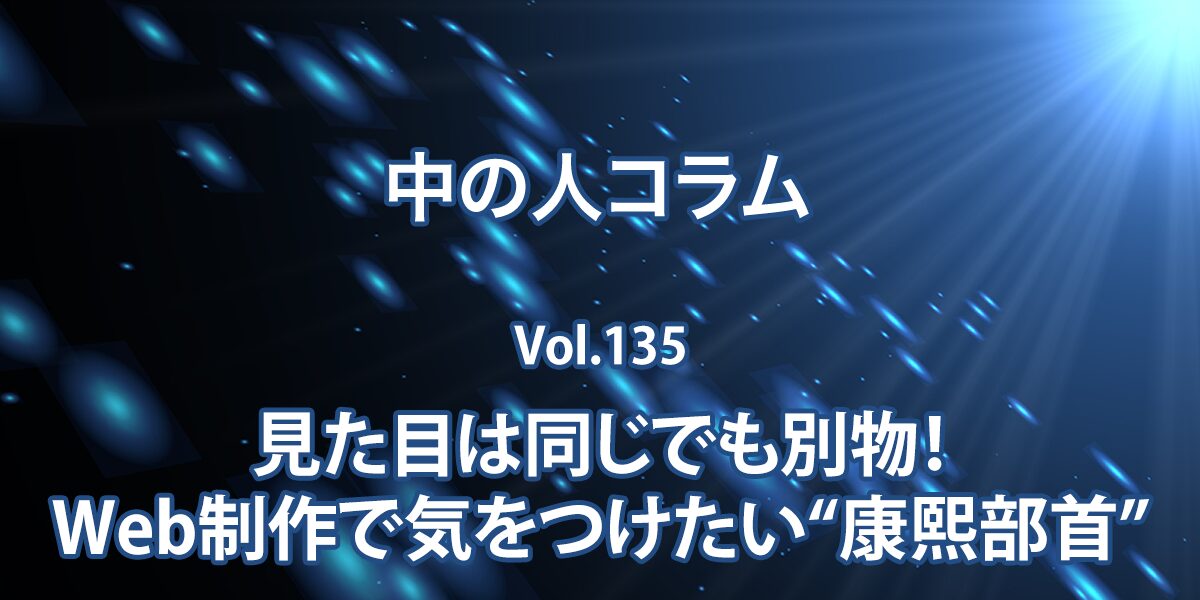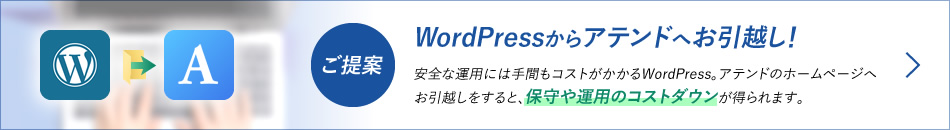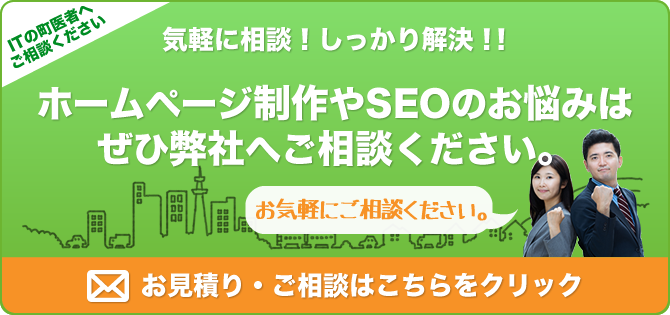Web制作や文章作成で、意外と気づかずに文字化けや検索不一致の原因になる存在があります。
それがUnicodeの「康熙部首(こうきぶしゅ)」です。
見た目は普通の漢字とほとんど同じ。でもコンピュータ上ではまったく別の文字として扱われます。
今回は、康熙部首とは何か、なぜ問題になるのか、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
それがUnicodeの「康熙部首(こうきぶしゅ)」です。
見た目は普通の漢字とほとんど同じ。でもコンピュータ上ではまったく別の文字として扱われます。
今回は、康熙部首とは何か、なぜ問題になるのか、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
漢字にそっくりな康熙部首とは
康熙部首とは、中国の康熙字典に収録された漢字の部首だけを別文字として登録したUnicodeの文字群です。Unicodeでは U+2F00〜U+2FD5 に割り当てられており、漢字文化圏の古典文献を正確にデジタル化する目的で作られました。
しかし、現代のWeb制作や文書作成では、思わぬトラブルを生むことがあります。
Unicodeの文字群について軽く補足
Unicodeとは、世界中の文字をコンピュータで統一的に扱うための国際規格です。アルファベットや数字、日本語の漢字だけでなく、絵文字や記号、古典文字まで含まれています。
その中の一部が「康熙部首」で、漢字の部首だけを抜き出した特殊な文字群です。
同様に、Unicodeには「CJK統合漢字」「CJK部首補助」「CJK互換漢字」など、漢字文化圏向けの文字群が複数存在します。
つまり、漢字に似た文字はWeb上にいくつも存在し、見た目が同じでもコードが異なることがあり、これが文字化けや検索にヒットしない原因になります。
見た目はそっくりでも別の文字
たとえば次の文字を比べてみてください。通常の漢字:入、山、日、米
康熙部首:⼊、⼭、⽇、⽶
このように、ほとんど区別がつきません。
こんなにも見た目が一緒でも、コンピュータ上では全く別の文字として扱われます。
この「見た目は同じでも別物」という特徴が、Web制作や文章作成で問題となる原因です。

同じに見えても、別の文字として扱われることによって起きる問題
1. 検索にヒットしない
Webサイトに「⽇」という文字が含まれていても、それが康熙部首の「⽇」だった場合、日本語の「日」で検索してもヒットしません。見た目では同じに見えるので、人間が読むことはできても、SEOの観点から見ると不利になるリスクがあります。
2. 文字化けすることがある
フォントや環境によっては、康熙部首が「□」や「?」のように表示されることがあります。特に古いブラウザやモバイル端末ではサポートされていない場合があり、表示崩れの原因になります。
3. URLやドメインの偽装に使われる可能性
康熙部首は、ドメイン名やファイル名に紛れ込むと、一見同じに見える別の文字として扱われます。そのため、フィッシングサイトや偽装メールのURLとして悪用される危険性もあります。
どうして康熙部首が文章に混ざるのか
意図せず文章に混ざるケースが多くあります。例えば…
・AI生成文章や翻訳ツールで変換されたとき
・OCRで文字を抽出したとき
・他サイトやPDFからコピー&ペーストしたとき
どれもやってしまいがちですね。
OCRで文章を読み取る際も注意が必要です。
また、この頃ではAIを活用して文章を作成したり、添削することも多くなっているので、AIで生成した文章にも注意が必要です。
康熙部首を見分ける方法
それではどうやって見分けるの?と思いますよね。見た目が一緒なので目視では難しいです。なのでツールを使うのが確実です。
1. Unicodeコードポイントを確認
Windowsなら「文字コード表(charmap)」macOSなら「文字ビューア」
文字を選択すると、通常の漢字と異なるコードであることがわかります。
2. オンライン判定ツールを使う
Unicode判定サービス(例:unifinder)正規表現で検出([\u2F00-\u2FD5])
Web制作やブログ更新時、納品前に確認しておくと安全です。
混入を防ぐための対策
・生成AIの出力は文字コードチェックを行う・フォント依存の特殊文字は避ける
・CMSやエディタに入力制限プラグインを導入する
・コピー&ペーストではなく、直接入力する
Webサイトへ入力する内容によってはコピー&ペーストやOCRは強い味方でもあるので、入力後にチェックできるツールを活用するとよさそうですね。
まとめ:文字の世界にも落とし穴がある
康熙部首は、漢字文化の歴史を保存する上では重要な存在ですが、現代のWeb制作や情報発信では思わぬトラブルを招く可能性があります。特に似た文字を扱う日本人にとっては見分けがつかないので、困る場面も出てくるでしょう。
康熙部首がWebサイト内に混入することによって
・見た目は同じでも別文字として扱われる
・検索にヒットしない、文字化けする、偽装のリスクもある
・コピー&ペーストやAI生成文章に紛れやすい
というリスクを理解して、しっかり対策していきましょう。
Web制作では、文字コードレベルでの正確さを意識することが重要です。
読者の皆さんも、文章やサイト更新の際には「見た目だけで判断せず、文字コードまで意識する」習慣を持つことをおすすめします。